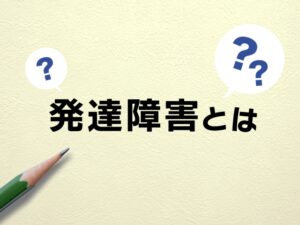お薬の処方が新しい場合【2025.09.08】
※ このページはプロモーション広告が含まれています
我が家の子供(長女)は、その時々の症状に応じて、お薬の種類を変更したり、今飲んでいるお薬の量を増量したり、減量したりと調整することがあります。
新しいお薬の処方をしてもらったら、薬局にお薬を取りに入って子供に飲ませるのですが、減量するときは比較的問題がないのですが、お薬の種類を変えたり、お薬を増量したりすると、たまに調子が悪くなる場合があります。
お薬の種類を変更した時や増量をした時に、ガックンと落ち込んだように静かになって落ち着いてくれる時はまだいいのですが、その逆でハイテンションになって暴れたりと、結構、飲んだ後の差が大きくでることがあります。
長男はお薬の調整もスムーズにいき、すぐに落ち着いて過ごせるようになったのですが、長女の場合、お薬の調整に時間がかかっています。
暴れても子供が小さいうちは、私が仕事中でも嫁さんが対応してくれていたのですが、子供も大きくなって親よりも力かついてくると、対応が段々と難しくなってきています。
いざ子供が暴れ出すと止めるのが大変で、妻も子供も怪我などをしてしまう危険性も出てくることから、お薬の種類の変更や増量をしたときには、できるだけ自分がお休みの土日祝や連休のときに、新しく処方してもらったお薬に変更して飲ませるようにしています。
本当は処方してもらったら、すぐに子供(長女)にも落ち着いて過ごしてもらいたいので、早く新しい処方のお薬を試してあげたいのですが、過去に大暴れして大変だったこともあります。
そのため、妻や子供(長女)が万が一、怪我などをしてしまわないよう、私が休みの時は、妻と子供の間に入って仲介ができるので、どちらも怪我などをしなくて済むことから、できるだけ自分が休みの時に新しい処方のお薬を試しています。
またそれだけではなく、子供は親が出すお薬はきちんと文句も言わずに全て飲んでくれますので、飲んだ後の様子を見て、病院の先生に新しい処方のお薬を飲んだ後どうだったのか経過を説明するためにも、よく観察のできる自分が休日の時に飲ませています。
あとお薬を飲んだあと、気分が悪くなったり、副作用がでた場合には、服用を止めて医師にご相談くださいとかよく書いてありますが、我が家の子供は自分でお薬を止めることもできませんし、自分で病院に行くこともできませんし、言葉で自分の意思表示や思いを伝えることができませんので、そんな理由もあってお薬の飲み始めを休日にずらすことがあります。
とはいえ、ずらしたとしても早く子供には落ち着いて過ごしてほしいですので、新しく処方されたお薬は必ず試すようにしています。
そのため新しい処方のお薬を始めるときは、よく観察をしてあげて、もし自傷行為が酷くなったり、他害が多くなったりした場合は、すぐに止めて病院の先生に報告するようにしています。
ゆえに新しい種類のお薬を処方された時や、増量したとき、減量したときもですが、調子が悪くなった場合は、すぐに止めて元に戻しても大丈夫かも聞いておくことが多いです。
逆に以前よりも調子が良くなってきた場合には、しばらくその処方で続けてみて、その様子を先生に結果報告し、継続する形をとっています。
子供が早く自傷行為なども無くなって毎日落ち着いて楽しく過ごしてくれるよう、お薬の調整も病院の先生と相談しながら進めていくわけですが、
たまに今まで飲んでいたお薬(エビリファイ内用液0.1%)で調子が良くなってきたので、1mgから3mgへ先生にご相談の上、ほんの少し増量しただけなのに、逆に自傷行為が酷くなってしまい、自分の髪の毛を全部自分で引っ張ってしまい、女の子なのに髪の毛が全て無くなってしまった可哀そうな経験が以前にあります。
それに新しく試したテグレトール錠200mgの服用では、睡眠時間が増加して起きれなくなってしまい、自傷、他害が増加した苦い過去の経験もあります。
その時もあまりの酷さにお薬を止めて先生に報告したのですが、落ち着いて過ごしてもらいたいのに、逆に苦しんでしまい、子供を見ていると辛くてとても可哀そうで仕方がありませんでした。
これは別にそのお薬を批判しているわけでもなく、たまたま自分の子供のその時の症状には合っていなかっただけで、そのお薬を飲んで落ち着かれたお子さんもたくさんいらっしゃったので先生も進めてくれたと思います。
他にも、オランザピンOD錠2.5mg(ジプレキサザイディス錠2.5mg)、オランザピン細粒1%、ジプレキサ細粒1%、ピレチア細粒10%などのお薬も、病院の先生の処方通りに試しましたが、飲んでも不調のままでした。
でも実際に試してみないと、そのお薬が子供(長女)に合っているのかどうかも分かりませんでしたので、良くても悪くても処方された「お薬の結果は今後の参考にするため記録しておくこと」にしました。
早く落ち着いて過ごせるようになった長男の時とは違い、長女にも早く落ち着いて過ごしてほしいのに、今のお薬の処方にたどり着くまでに相当の時間がかかりました。
今は昼頃は調子が悪くなりますが、以前に比べるとだいぶん落ち着いてくれていて、
朝に、バルプロ酸ナトリウムSR錠200mgを1錠。(※ 昼頃、調子が悪くなるので2錠に変更予定、仕事が連休の時に始めます) 頓服は、リスペリドン細粒1%(0.1g)平均1日、2~4回服用。 就寝前は、バルプロ酸ナトリウムSR錠200mgを1錠とジプレキサ細粒1%(1.2g)+リスペリドン細粒1%(0.25g)が混合になったもの1包、飲ませています。 朝も決まった時間に起こすと、たまに夜更かし(障害が無くても寝付けない時は誰にでもありますので)もありますが、ほぼ毎日ちゃんと寝てくれています。 ですが今ではちゃんと寝てくれていますが、お薬が合わず酷い時には、1週間で平均2回位は寝ない時期が長い間続きましたので、就寝前のお薬の調整が落ち着くまでは本当に大変でした。 周りのご近所の方も夜中で寝ているので、子供には静かに過ごしてもらわないといけませんので、興奮する前に子供用のご飯を作って食べさせてあげたり、おやつをあげたり、YouTubeの動画を小さい音量で見たり、本を静かに見たり、胸をトントンして寝かしつけたりして対応をしなければいけなかったですので、そのときは毎週2日間位は寝ずにそのまま仕事に行っていましたので、自分自身が倒れてしまわないか心配しながら仕事に行ってました。 かと言って毎日の生活もあり毎月お金も必要ですので、仕事を休むわけにもいきませんでしたので、その時は凄くしんどかったです。 就寝前のお薬の種類は確か変更しなかったと思うのですが、就寝前に飲むそれぞれのお薬の量を微妙に増やしたり減らしたりして先生に調整をしてもらって、やっと落ち着いて寝れるようになりました。 そんな過去の経験もありますので、今では毎日寝れることに喜びを感じています。 当時は自分も寝不足でイライラしてしまうこともたまにありましたが、そうすると同じように子供にも伝染して、夜中なのに子供も調子が悪くなってしまいますので、いくら疲れていてもできる限り穏やかに接してあげるよう心がけていました。 ですが、子供のことを悪いと思ったことは、当然ですが一度もありません。 もちろん、お薬の処方の問題だけではなく、お腹が減っていたり、おやつが欲しくなったり、お外に散歩に出かけたかったり、早くお風呂に入りたかったり、体の調子が悪かったり、早く寝たい、寝ようとしても目がさえて寝れないなど、他の原因もいっぱい考えられます。 しかし子供は自分の言葉で意思表示することができませんので、洞察力を磨き、手振りや視線や体の動きなどを見て判断してあげ、気配りや思いやりをもって接してあげないといけません。 それだけにお薬の処方が新しい場合、特に新しいお薬の種類を飲ませるときや増量したときは、過去の経験から、注意深く観察して見守ってあげる必要があると考えています。 お薬が合っていたら何の問題もなく続けていけるのですが、もし合っていない場合、すぐに止めて上げれるのは、毎日、子供のことを見ている親だけになりますので。 たった一度の処方でお薬がピッタリと合って落ち着いてくれていたら、こんなにも長い間心配しなくて済んだのですが、なかなかお薬の種類や微妙な量で子供の調子が変わってしまうので、思春期やその時々の時期にもよるとは思うのですが、お薬の調整は難しいなあと実感しています。 けれど子供が早く落ち着いて、毎日、笑顔で楽しく過ごしていけるようになってほしいですので、そのための努力は惜しみません。